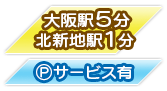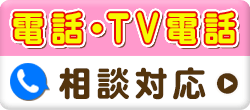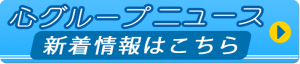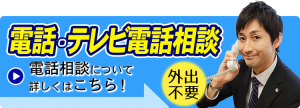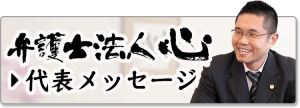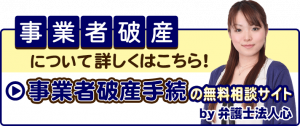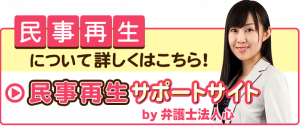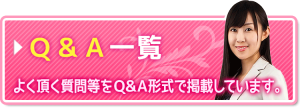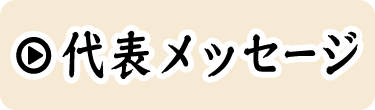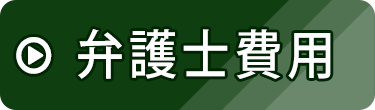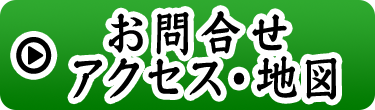会社破産をすると経営者はどうなるか
1 会社の運営からは外れ、経営者自身も自己破産せざるを得ないことが多い
会社の経営が行き詰ってしまい、会社破産の申立てをすると、会社の債務や資産の管理、清算業務等は破産管財人に委ねられます。
経営者は会社の運営ではなく、破産管財人の業務に協力する立場になります。
また、特に中小規模の会社においては、経営者が会社の債務の連帯保証人になっていることも多く見受けられます。
会社の債務が大きく、経営者も連帯保証している債務の返済ができない場合、自己破産をせざるを得ないことがあります。
以下、経営者の方の自己破産の流れと、自己破産による生活等への影響について説明します。
2 自己破産の申立て
自己破産を申立てる際には、経営者の個人的な収入、支出の状況、財産、債務の状況を精査し、申立てのための書類に記載する必要があります。
会社の財産と経営者個人の財産の区別が曖昧である場合、綿密な調査が必要となります。
収入や支出については、家族が家計を管理している場合、協力を得て調査をすることになります。
資料が揃ったら、裁判所に自己破産の申立てをします。
会社破産と同時期に申し立てることも多いです。
3 破産手続きによる財産の換価、免責
破産手続きが開始されると、経営者個人の財産についても、生活の維持に最低限必要なものを除いて破産管財人が換価をします。
換価して得られた金銭は、債権者への返済に充てられます。
経営者個人が所有する自宅不動産や自動車なども、基本的には換価の対象となりますので、転居先や移動手段を確保する必要があります。
財産を換価して得られた金銭をもってしても支払い切れなかった分については、免責が許可されることで、返済の義務を免れることができます。
4 自己破産後の就業等について
会社破産をすると、最終的には会社が消滅しますので、これまで会社から得られていた役員報酬などの収入はなくなります。
自己破産によって、経営者個人の財産も大半を失うことになりますので、今後の生活を維持するためにも、収入を得ていかなければなりません。
収入を得る手段は、一般的には、他の会社等に就職するか、新たに起業するかが考えられます。
まず、就職をする場合、自己破産の手続き中は一定の職業に就けないという制限がありますが、復権(多くの場合免責決定)後であれば制限はなくなります。
起業については、新しく会社を作るか、個人事業を開始することになると考えられます。
自己破産をしていても、法律上はこれらが制限されることはありません。
ただし、自己破産から7年間程度は、信用情報に事故情報が登録されるため、金融機関等から融資を受けることは困難になります。